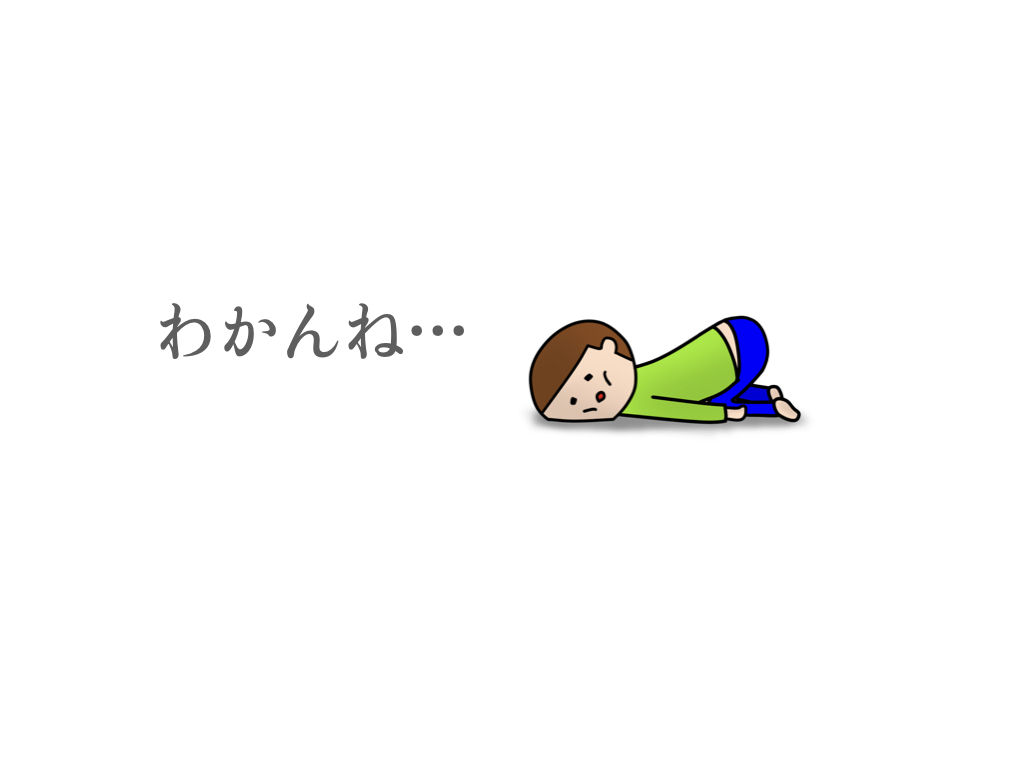よくある「ウェブ制作会社の乗り換え理由」
今回はウェブ制作会社を乗り換える際に気をつけることを「4つの手順」でご紹介します。
制作会社を変えたい理由は各社によって異なると思いますが、実際に当社に寄せられる相談ごとのざっくり統計を見ると、
「保守管理費用が高い」
「デザインがダサかった」
「SEOの順位が上がらない」
「運営後の修正対応が良くない」
「リニューアルしたかったので」
以上のような理由が多いようです。
「制作会社の変更」は結構大変なことのようにも思えますが、必要なことはほぼ共通しているんですね。費用対効果の薄さ、単純にダサい・使いにくい、制作前のやたら素敵な提案書と完成後の落差…などなど。
「4つのステップ」で見る乗り換え方法

では、ホームページ制作を乗り換えることを決定した際に、まずは何をすればいいのでしょう?
一方的に制作会社に別れを告げても、さまざまな「足かせ」がすでにあった場合、そう簡単にはいかずかえって揉め事に発展してしまいます。
会社間のこと、特に委託業者の乗り換えのケースは慎重に進めるとストレスも低減できますので、急がば回れで賢く進めましょう。
ではウェブ制作会社の乗り換え手順を「4つの手順」に分けて見ていきます。
【手順①】弁護士に伝える

弁護士と契約している場合は、以降に解説する【手順①】【手順②】に入ることを伝えておきましょう。
法的な解釈や契約書、著作権に関することは素人にはなかなか難しい場合もあるからです。
弁護士と契約してない場合は、決して自力で乗り切れない内容ではないので、以降の手順に進みましょう。ただし、制作会社が不親切な対応をとったり、不可解な請求をチラつかせてくる場合、音信不通になるなどのケースによっては法的なサポートを準備するのが安全です。
【手順②】まずは契約書をチェック

何はともあれ「契約内容」をチェックです。例えばわりと罠の多いリース契約などしていると、契約解除が難しかったり、高額の契約破棄費用がかかってきたりします。
結論、そういう場合も(そういう場合こそ)いっそ乗り換えてしまったほうがいいのですが、まずは契約書をチェックしましょう。
解約解除については『ウェブ制作会社との「契約解除」で気をつけたい「3つの注意点」』も、のちほどチェックいただくとさらにGoodです。
【手順③】著作権をチェック

わりとモメることの多い「著作権」にも注意です。
サイト内で使用されているロゴ、デザイン、キャッチコピーや現行、写真に動画などは御社と制作会社のどちらに著作権が帰属するでしょうか。
「制作費用は払ったが、そのなかに著作権譲渡は一切含まれてない」というには普通にあるケースですので、必ず事前チェックが必要です。
また、写真や動画などは使用期限が決まっている場合もあるので、制作会社に「制作会社に帰属している著作権部分」「写真レンタル会社等にある著作権」そして「自社が持つ著作権」をきちんと確認しておきましょう。
著作権に関するトラブルは別記事「ウェブ会社にだまされた?ホームページ制作物の著作権問題」でも取り上げています。
【手順④】乗り換えに必要な情報をチェック

契約書、そして著作権をチェックできたら、いよいよ各論に入っていきます。
以下の「4つの情報」を整えましょう。
1)ドメインの情報
ドメインとは「~~.com」「~~.net」などのURLですね。英語でなので感覚がつかみにくいですが「サイトの住所・表札=ドメインという意味合いです。このドメインを「制作会社が契約・管理しているか」「自社で行っているか」をチェック。
もし自社でない場合は、ドメイン管理会社のログイン・IDの情報が必要となります。もし、制作会社がさまざまな他社のドメインを1つのアカウントで管理している場合などは「登録者名義の変更」も必須です。
2)サーバーの情報
そしてウェブサイトが置いてある「サーバー」の契約情報もチェックです。こちらもドメイン同様のアカウントのIDとパスワードが必要です。これは、サーバー管理会社の「コントロールパネル(管理画面)」に入るためです。
また「FTPやSSH」などの「サーバー接続情報」も必須です。こちらは、制作会社がサーバーに接続し作業するために使用している情報となります。
ドメイン同様、制作会社に契約代行・運営代行してもらっている場合は名義の変更が必要となります。
3)CMSのログイン情報
これは、例えばワードプレスなどのCMSでサイトを構築している場合、そのCMS内にログインするためにアカウント情報のことです。IDやパスワード等のことですね。
単にログインできれば良いわけでなく、サイトを管理するうえでの最高権限「管理者」を付与してもらう必要もあるので忘れずに。他のステイタス(編集者、投稿者など)では、完全にそのCMSを管理できないので気をつけましょう。
同時に、新規の制作会社との契約が決定して実際に運用が移行するタイミングなどで、これまで管理していた会社の管理権限を然るべきタイミングで削除する必要もあります。
4)ソースコードの情報
そして最後に、サイトを形作っているデータ(ソースコード)一式を譲渡してもらいます。
ソースコード一式にはHTMLサイトやCSS,写真などの画像データなどすべての要素が含まれます。
前述のCMSでサイトを制作している場合は、データをダウンロードできる簡単なプラグインもあります。
乗り換え先の制作会社に相談を
以上の【手順①②③④】をチェックし整理できれば、制作会社移行の準備はOK。
わからない箇所は多々あると思いますので「乗り換え先の制作会社に必要なものを聞く」ことで慎重に進めていきましょう。
なぜなら、契約解除されるほうの会社が必ずしも親切だとは限らないから。そういうところでその会社の素顔が見えたりもするので、よく人間(会社)観察しておきましょう。
特に【手順④】は専門的な話になるので、よくわからない場合はお気軽にご相談ください。
「会社を変えたらURLやメアドも変わっちゃうの?」
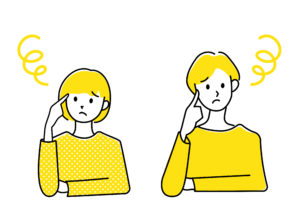
ところで、よくあるご質問で「制作会社を変えたら、URLとかメアドも変わってしまいますか?」というのがございます。
結論、変わりません。
ごくごく稀なケースで、現在のウェブ会社との契約が「ドメイン使用の禁止」がある可能性もなくはないですが、そういったことはほとんどありませんので、もしあったとしても泣き寝入りせず、弁護士に相談するのが良いでしょう。
サイトのURLが変わるデメリット
「ウェブサイトのURLが変わっても、リフレッシュってことOK!」なんて思ってはいけません。
サイトのURLが変わると、Googleからのサイトの評価は「ゼロ」に戻ります。つまり、検索順位で上位にあった記事やページが100位圏外に飛ばされるなんてことは普通にあるんですね。
WEBページのURLは「大切に育ててきた財産」という認識をもって「死守」できるようにしましょう。簡単に変えてはいけません。
段取りを組んで慎重な乗り換えを

今回解説した内容は、記事内にもある通り「弁護士」や「乗り換え先の制作会社」のサポートを受けることができる内容です。
例えば社長さんなら一人でやろうとせず、あるいは会社内のウェブご担当者さんなら一人で背負い込まず、アドバイスをもらいながら進めましょう。
内容はなんとなく複雑にも見えますが、ドメインやサーバーの権限移行や名義変更などは、ウェブ制作会社にとっては日常業務の一貫でもあり、決して難しいミッションではありません。
解約解除については『ウェブ制作会社との「契約解除」で気をつけたい「3つの注意点」』も、同時にチェックいただくとより知見が深まるかと思います。
当社でも、乗り換え前のご相談はもちろん承りますので、お気軽にフォームよりご相談くださいね。