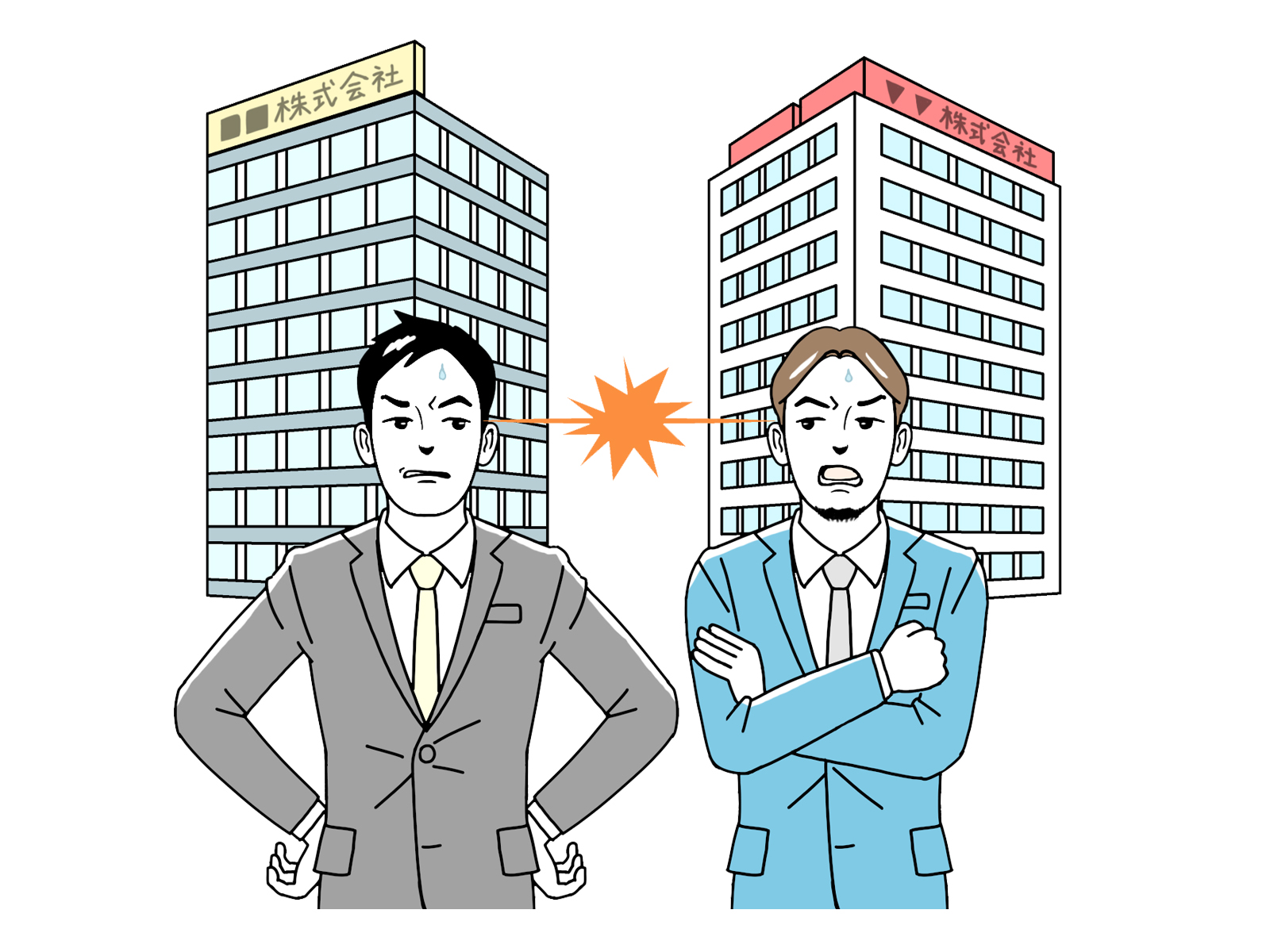「競合調査」が9割
ホームページを良くしたい場合。
兎にも角にもやるべきは「競合調査」です。
競合サイトには「ヒント」しか詰まってない。いや「答え」が詰まっている。(※パクリはダメね)
ウェブづくりは「競合調査が9割」と言っても過言ではないんですね。
まだピンとこない方も、ぜひ今回この重要さをご理解いただければと思います。
全ての根底にある「競合」との兼ね合い

「自社のサイトの作り方は果たして正しいのか?」
「なんか競合サイトのほうが良く見える」
こんな感覚、自社のWEBサイトを気にしている社長さんやウェブのご担当者さんならあるかと思います。
しかし、それを確認するための術がない…って感じで息詰まる。
答えは「競合サイト」が持っています。
パクリは禁止ですが、ヒントをもらい、さらに良くアレンジすることで突破口が開けるんですね。
では競合調査をどう自社のサイトに活かすのかを「3つのステップ」で見ていきましょう。
競合調査「3つのSTEP」
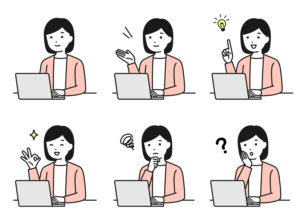
競合調査をきちんとやるかやらないかで、WBEサイトの明暗が分かれます。以下のステップで進めます。
【STEP①】
ライバル会社、憧れの会社のサイトを3〜5社集める
まずはライバル会社、同業会社、憧れの同業社などをピックアップしましょう。
【STEP②】
各社のWEBサイトの特徴を表でまとめる
デザイン、ターゲット、メイン商品、使いやすさ、マイナス点、さらに「スマホサイト」の特徴をまとめます。ようは「目についた良いところ」をざっくばらんにでOKなのでピックアップするんですね。完璧は目指さないで大丈夫、ちょっとでもやることが大事。
【STEP③】
①②を経て自社のサイトを改善する
ひとつでもアレンジして使えることがあれば、自社のサイトに反映します。
以上の流れです。
このシンプルな作業を日々繰り返す。1週間やるだけでも結構な量が出てくるはず。
ライバルサイトを謙虚に参考にすることで、自社に足りなかった点が具体的に見えてくるんですね。これが競合調査のいいところ。
競合調査が大事な「3つ」の理由

なぜ競合調査が大事なのでしょう?
「サイト改善」に目線が行きがちですが、ここはとても大事なところ。
①「ライバル会社の現在」がわかる
②「自社の弱み・強み」を再確認できる
③「どんなサイトにすべきか」がわかる
当てずっぽうや好みでなく、制作会社やデザイナーに言われるままでなく、自分・自社のなかで「こんなサイトがいい」というのが見えてきます。
デザインや導線、ターゲット、商品の目立たせ方、キャンペーン、スマホサイトの特徴に至るまで、自社サイトの目指すべき方向性がわかるのです。
ちょっと専門的な言葉を使えば、マーケティングでいう「3C(Customer:市場・顧客/Company:自社/Competitor:競合)」に通じる、商売のや要件定義の本質なところ。
競合調査は制作会社に依頼してもOK

「競合のパクリはいけませんが見習うところは見習ってより良くする」
「ライバル会社の弱点を把握したうえでの打ち出しができる」
こういったさまざな点で、自社のサイトでやるべきことが具体的に抽出できるのが競合調査の醍醐味。
もし自社のスタッフでの調査がしんどい場合は、ホームページ制作会社に依頼しましょう。いきなり制作を頼むのでなく、まずは競合調査をしてもらうことで、制作会社自身にもその市場を理解してもらえます。自社のマーケティングチームにとっても有益な情報になりますね。
中には、競合調査をしない制作会社も多々ありますので、こちらからハッキリとオーダーするのが確実です。
競合調査が9割
ホームページ制作は競合調査が9割。
ここで全てが決まると言っても過言ではありません。この概念はSEOにも使えます。
こうした作業をまとめて可視化していくのが「要件定義書」となっていきます。
まずはライバルサイトをいくつか出して、いったいどこに魅力を感じるかをできる範囲で書き出してみましょう。