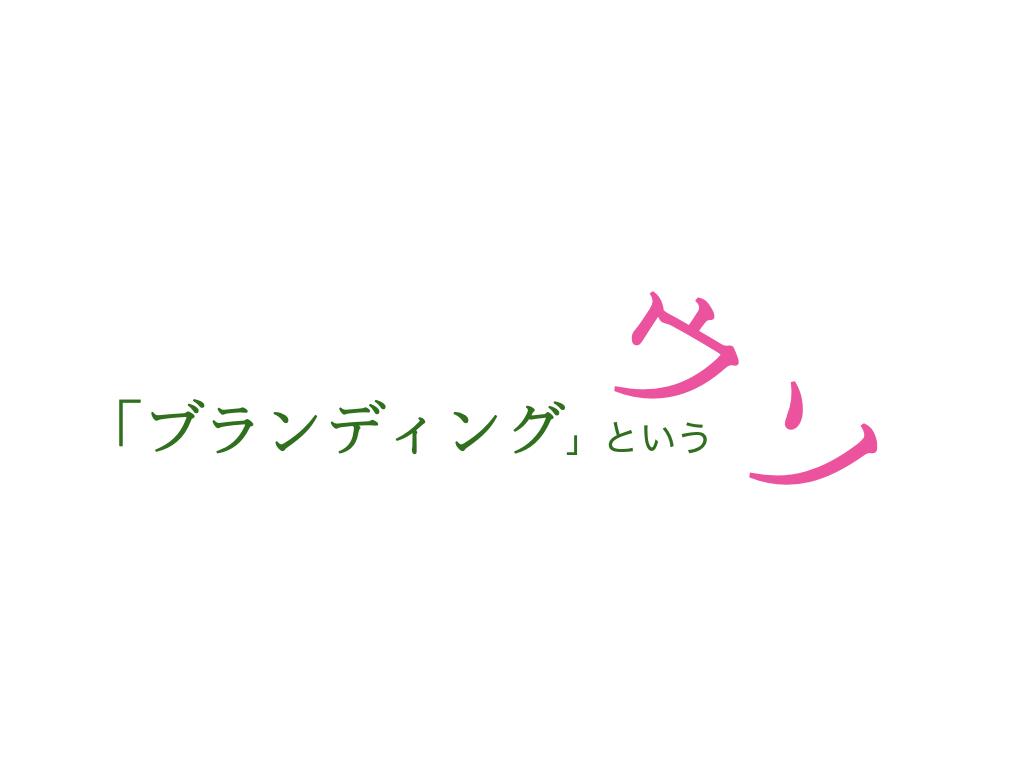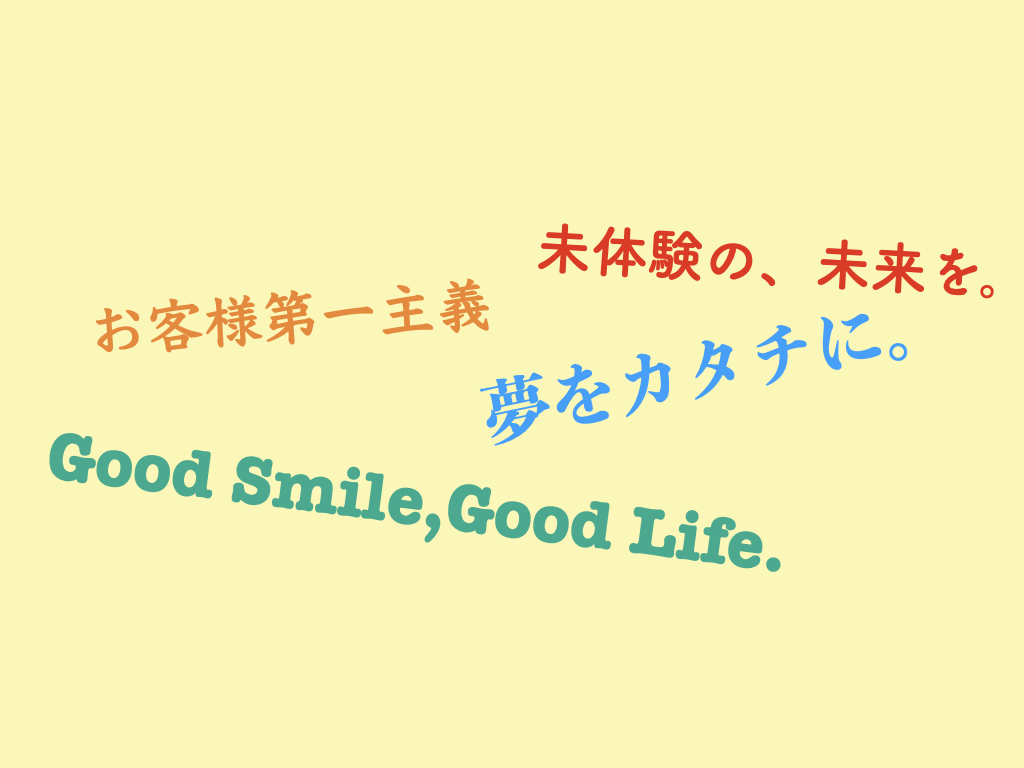ウソだらけのブランディング
ハンバーガーの写真はとてもおいしそうなのに、出てきたものはペチャンコだった。
「まあ、でも、こんなもんでしょ」
こうして許してきた客側も悪いのですが、やはり大元の企業が諸悪の根源です。もっと言うとそれをプロデュースしているブランド演出の企業が戦犯であり共犯です。
ハンバーガーの例に溺れず、一般の企業も「ブランディング」なる横文字で意味がボカされることで罪悪感を失い、限界まで自社や製品を素敵に見せまくる。
これが現代のブランディングの実態と言えるでしょう。
しかし、やらなければ勝てない?

しかしこの競争社会において、競合他社が事実を捻じ曲げ素敵度MAXで製品を演出してたら、自社でも負けじとやらざる得ないというのが市場でも普通のことになっています。
そういった企業のジレンマに漬け込むのが、ブランディングのプロデュース会社であり、ウェブや紙媒体の制作会社であり、広告代理店などの企業。彼らも商売ですから、ブランディングは生き残るための必須手段という名目で営業してくる。
ブランディングで事実を捻じ曲げつつ、まずは市場で目立つことを優先する。「ウソではない理論」をフル活用して、とりあえずを繕う。この状況が終わることはないでしょう。
実態を隠す逆SEO・逆SNS施策

自社のリアルな悪評を隠すために「逆SEO」を行い、実態をさらしている記事の順位を下げる。
SNSでの口コミを隠蔽できるように、無数のやらせ口コミをSNSに大量に投下する。
これをやっても、この時代、完璧にリアル口コミを封じることは不可能ですが、それでもやはり効果はあります。インターネット検索のライトユーザーなんかは、ディープな情報まではたどり着かないので、事実上の隠蔽には成功することも。
こういったことも「ブランディング施策」のひとつとして存在している世界線にいま私たちは生きているんですね、なんとも。
試される自制心

ブランディングのプロデュース会社やウェブや紙媒体の制作会社は、いくらでも素敵に見せようとします。
序盤の要件定義を大いにプラスにとらえ、尾ひれ羽ひれをつけて、素敵なことだけをサイトに記載する。まさに「意味ないブランディング」ですね。
そこで試されるのは「発注側の自制心」でもあります。
制作会社に対して「それはウソではないが事実と異なる」「大げさにとらえすぎ」「そんなに盛るとつじつまが合わない」など、抑制することが必要。
本来は、制作側がそれをやらないといけないのですが、提案時にあまりに地味にものは持っていけないという背景があります。
ブランディングを「リアル」「正直」にシフトを
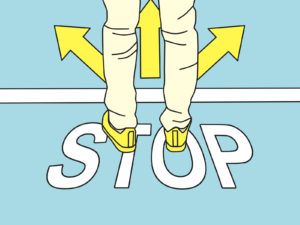
もし今後、御社がブランディングをすることになった場合。
よくあるパターンとしては「ウェブサイトのリニューアル」のとき。そんなときは「盛るブランディング」を導入せず「リアル」「正直」を追究してみてください。でないと、良いことだけ書いてあるウェブサイトが完成してしまいますよ。
キラキラしていて金だけはたんまりかかるブランディング、そういった提案をしてくる会社は時代遅れであり、そもそも「ブランディング=素敵に見せる」と勘違いをしていますから、御社は「金を払ってウソをつく」ことに加担してしまいます。断ったほうが、御社もトラブルに巻き込まれるリスクを回避できます。
勝てる戦略とは、決してウソをつくことではありません。
誘惑に勝てるかどうか、ここがまずブランディングの第一歩だと考えます。